☆☆☆Amazonレビューなんか見るな
さて、書評なんだか御自説の展開なんだか良く分からなくなってきた。
まだ本筋を一行も書いてないことには戦慄するが、それは2行だから大丈夫。
安心して蛇足に付き合ってほしい。
僕はAmazonのレビューを見ない。点数なんかなおさら見ない。本から受け取る直感を、
標準化なんてできるか、と本気で思っている。
最近、有名人(というか内田樹)が実名でレビューを書いていたりするのを見るにつけ、
これって反則では? なんて思うこともある。だって、こういうレビューってそもそも、
業界に影響力のない”素人による実感”を反映するための仕組みじゃなかったのか?
これじゃあ有名人の独壇場じゃん。
しかも、その影響力ってマスな媒体で有名になったからこそ出現したわけで。
マスVSアンチみたいに考えすぎるのかもしれないが、なにかつまらない。
半日沈思黙考した挙句、「参考にならなかった」ボタンを僕はこっそりと押したのだった・・・
仮にも本を薦めるならば「こんなことが書いてあります」だけではもったいないと思う。
もちろんそれでもいい書評はたくさんある。でも、自分の立ち位置を明確に打ち出すことで
賛同も批判もVividなものになる。そして、書評にとって大切なのは、薦める本を読む人の
読書体験がVividになることではないだろうか?
というわけで、異常に長かった前置きは終わり、僕はポジションを取ることにする。
子どもの不平等とは、やれば報われると信じられるマインドの有無
今日の1冊をようやく紹介できる。この本には、次のようなことが書いてある。
『努力したら報われる』と感じられること自体が、社会の上層にいる者の特権だ。
子どもを取り巻く不平等とは、『努力したら報われる』と信じて生きていける子と、
そんなことを信じられない子との差。だから、子どもを取り巻く不平等を無くすには、
『努力したら報われる』(少なくとも可能性はある)と誰もが信じられるようにすることだ。
簡単にまとめるなら、子どもの不平等とは、やれば報われると信じられるマインドの
有無である、ということ。
「努力したら報われる」という自己肯定感を信じられるために必要な要素
これを踏まえた僕のポジションを、約束どおり2行で書こう。
「努力したら報われると信じられるために必要なのは3つ。
使い道を決められる金・相談できる大人・数回の失敗が不利にならない制度だ。」
僕のポジションは、まごうことなく上の本の受け売りだ。
臆面もなくこう言うのは、僕がこの本に書いてあることを(とても珍しく)信用しているからだ。
その理由は、この本が上に書いた「問題の立て方」を忠実に実行しているからであり、明確に
ポジションを取っているからであり、可能な限り統計的な正当化を試みようとしていることによる。
統計学が「最強の学問」かどうかは知らないが、少なくとも統計的な裏づけが、仮説の強力な
正当化方法であることは確かだ。
残念なことだが、こういう本は、非常に少ない。そして売れない。
店頭に並んでいるものや人気のあるものは、極端で印象的な表現で埋め尽くされている。
「日本沈没」とか「無縁社会」とか「前田敦子はキリストを超えた」とか。
一分の真実も含んでいない本というのはたぶんないと思うが、ただ楽しんで読めればいい、
という態度は時にアブナイと個人的には思う。人は、割と簡単にダマされる。
だから、苅谷氏のこの本は良心的で、貴重だと感じる。僕は大いに感心したのだった。
ここまで読んでくださった皆さんには、是非試みに読んでみてほしい。
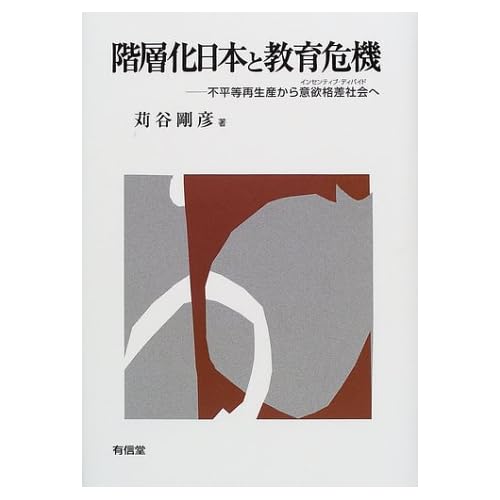




0 コメント:
コメントを投稿