☆
いきなりだが、うちの母ちゃんは体重80キロオーバーのOh-De-BOOである。
昔はときどきダンベル体操したりしていたが、最近は地道に食べる量を減らそうと試みているらしい。
そんな母ちゃんは私が生まれてかれこれ30年来、テレビを見ながら「人間は不平等だ!」と憤っている。
この前、De-BOOは直らないんだから年金をたくさんもらうべきだ! と滅茶苦茶なことを言ってみたら、
大いなる賛同をいただいた。(ちなみに、母ちゃんはこのブログは絶対に見ない。私はとても安心である。)
私たちの世界は差でできている。確か、ソシュールだったか誰かがそんなことを言っていた。
言語とは、差によって世界を切り出すシステムなのだ、という意見だ。
差が意味を作り出す。だから、差がなければ意味も存在しない。
もしそうであるならば、一般的に言って、差があることそのものが悪だという考えには与しがたいだろう。
実際には、私たちは差を憎むことがよくある。それは、身体的特徴だったり、自由になるお金の量だったり、
バレンタインデーに貰ったチョコレートの数だったりする。
でも、憎まれない差もある。テニスが趣味の僕は、友人がサッカーをしているからといって恨んだりはしない。
恨まれるほうだって、全く謂れのない差というものもある。例えば古代ギリシアだ。
当時のギリシアというのは奴隷社会で、市民は基本的に生産活動に従事しなかった。
では何をやっていたかといえば、それは政治だ。
(そして、それでもヒマを持て余していた人たちが、昼寝しながら夢想しているうちに・・・、「愛知」学なんぞという
妖怪を生み出してしまったのだが、これはまた別の話。)
面白いのは、ソ―クラテ―スもアリストテレ―スもプラト―ンも、「なぜ市民と奴隷のあいだには不平等が
存在しているのか」とは決して問わなかったということだ。そもそも「平等な権利を持った主体(としての人間)」
という観念はなかったので、不平等に思い至る契機などなかったのである。
この違いは何なのだろう?
少し考えてみると、僕たちが差を憎む場合、その前頭辞として「本来なら私もああであるべきなのに」
という意識がくっついていることが分かる。これこそが、平等―不平等という問題のポイントだと僕は思う。
今回はこの平等―不平等について少しだけ考えてみたい。
この書評は、担当がテーマを設定し、3人の評者がそれを書く、というものなのだが、今回のテーマには
全く困った。だって、「平等」、と来たもんだ・・・
あまりにも何も考え付かないから、Amazonで「平等」とキーワード検索して15番目くらいの知られすぎてない
本を選んで、こんな本を紹介します!、とやろうかと一瞬考えたのだが結局思いとどまった。
思いとどまったのには理由がある。それは、問題はいい加減に立ててはいかん! という天の声が
鳴り響いたからだ。
(ちなみに、実際やってみると、『キング牧師-人種の平等と人間愛を求めて』 (岩波ジュニア新書)が出てきた
ので、とても悪いことをした気持ちになった。)
問いの立て方は、たいへん重要だ。
問いの立て方が下手だと、結論も下手になり、結果として行動も下手になる。
じゃあどんな問いの立て方が上手くて、どんな問いの立て方が下手なのか?
大体こんな感じである。↓
何が良くて何が悪いのか?
それは、設定が具体的かどうかに加えて、「ポジションを取った」問題の立て方が良い、ということだ。
最近のビジネス本にはよく書いてあるし、マッキンゼーの問題解決テクニック(みたいな本を書いたマッキンゼー
出身者は20人くらいはいる)とかにもよくある話なので、こういう本を読む人には真新しさはないかもしれないが、
全くその通りだと思う。なぜかと言うなら、それは次のような理由による。
理由① 漠とした問題設定だと、何から調べれば答えにたどり着くのか分からない。迷う。
理由② 結果、見通しもなく、網羅的にやる、という方向に流れやすい。
理由③ 結果、時間がかかりまくる。
理由④ 結果、途中で飽きてくるので、思考・作業に濃淡が出る。
理由⑤ 結果、無意識に、正しいと思いたいことを無理やり正当化する羽目になる。
だから、まず具体的な仮説から入って、次に、何が言えればその仮説を正当化できるかを考え、その点に
絞って調査を実施する。そして、調査結果から仮説を検証して、修正する。あとはこれを繰り返し、
行動に移せるレベルになったら即実行する。とてもスマートな方法論だと思う。
いきなりだが、うちの母ちゃんは体重80キロオーバーのOh-De-BOOである。
昔はときどきダンベル体操したりしていたが、最近は地道に食べる量を減らそうと試みているらしい。
そんな母ちゃんは私が生まれてかれこれ30年来、テレビを見ながら「人間は不平等だ!」と憤っている。
この前、De-BOOは直らないんだから年金をたくさんもらうべきだ! と滅茶苦茶なことを言ってみたら、
大いなる賛同をいただいた。(ちなみに、母ちゃんはこのブログは絶対に見ない。私はとても安心である。)
私たちの世界は差でできている。確か、ソシュールだったか誰かがそんなことを言っていた。
言語とは、差によって世界を切り出すシステムなのだ、という意見だ。
差が意味を作り出す。だから、差がなければ意味も存在しない。
もしそうであるならば、一般的に言って、差があることそのものが悪だという考えには与しがたいだろう。
実際には、私たちは差を憎むことがよくある。それは、身体的特徴だったり、自由になるお金の量だったり、
バレンタインデーに貰ったチョコレートの数だったりする。
でも、憎まれない差もある。テニスが趣味の僕は、友人がサッカーをしているからといって恨んだりはしない。
恨まれるほうだって、全く謂れのない差というものもある。例えば古代ギリシアだ。
当時のギリシアというのは奴隷社会で、市民は基本的に生産活動に従事しなかった。
では何をやっていたかといえば、それは政治だ。
(そして、それでもヒマを持て余していた人たちが、昼寝しながら夢想しているうちに・・・、「愛知」学なんぞという
妖怪を生み出してしまったのだが、これはまた別の話。)
面白いのは、ソ―クラテ―スもアリストテレ―スもプラト―ンも、「なぜ市民と奴隷のあいだには不平等が
存在しているのか」とは決して問わなかったということだ。そもそも「平等な権利を持った主体(としての人間)」
という観念はなかったので、不平等に思い至る契機などなかったのである。
この違いは何なのだろう?
少し考えてみると、僕たちが差を憎む場合、その前頭辞として「本来なら私もああであるべきなのに」
という意識がくっついていることが分かる。これこそが、平等―不平等という問題のポイントだと僕は思う。
今回はこの平等―不平等について少しだけ考えてみたい。
問いを立てる
全く困った。だって、「平等」、と来たもんだ・・・
あまりにも何も考え付かないから、Amazonで「平等」とキーワード検索して15番目くらいの知られすぎてない
本を選んで、こんな本を紹介します!、とやろうかと一瞬考えたのだが結局思いとどまった。
思いとどまったのには理由がある。それは、問題はいい加減に立ててはいかん! という天の声が
鳴り響いたからだ。
(ちなみに、実際やってみると、『キング牧師-人種の平等と人間愛を求めて』 (岩波ジュニア新書)が出てきた
ので、とても悪いことをした気持ちになった。)
問いの立て方は、たいへん重要だ。
問いの立て方が下手だと、結論も下手になり、結果として行動も下手になる。
じゃあどんな問いの立て方が上手くて、どんな問いの立て方が下手なのか?
大体こんな感じである。↓
| 巧劣 | 問題(問い)の立て方 |
| 一番ダメ | 「平等とは何か、考えてみよう!」「日本は不平等社会かどうか? |
| だいぶまし | 児童養護施設で生活する子どもたちは、そうでない子どもたちと比べて 不平等な環境にされられていると言えるか? それは具体的に何か? |
| 良い | 無利子の奨学金が充実すれば、子どもたちは不平等から解放されるか? |
「ポジションを取った」問題の立て方
何が良くて何が悪いのか?
それは、設定が具体的かどうかに加えて、「ポジションを取った」問題の立て方が良い、ということだ。
最近のビジネス本にはよく書いてあるし、マッキンゼーの問題解決テクニック(みたいな本を書いたマッキンゼー
出身者は20人くらいはいる)とかにもよくある話なので、こういう本を読む人には真新しさはないかもしれないが、
全くその通りだと思う。なぜかと言うなら、それは次のような理由による。
理由① 漠とした問題設定だと、何から調べれば答えにたどり着くのか分からない。迷う。
理由② 結果、見通しもなく、網羅的にやる、という方向に流れやすい。
理由③ 結果、時間がかかりまくる。
理由④ 結果、途中で飽きてくるので、思考・作業に濃淡が出る。
理由⑤ 結果、無意識に、正しいと思いたいことを無理やり正当化する羽目になる。
だから、まず具体的な仮説から入って、次に、何が言えればその仮説を正当化できるかを考え、その点に
絞って調査を実施する。そして、調査結果から仮説を検証して、修正する。あとはこれを繰り返し、
行動に移せるレベルになったら即実行する。とてもスマートな方法論だと思う。
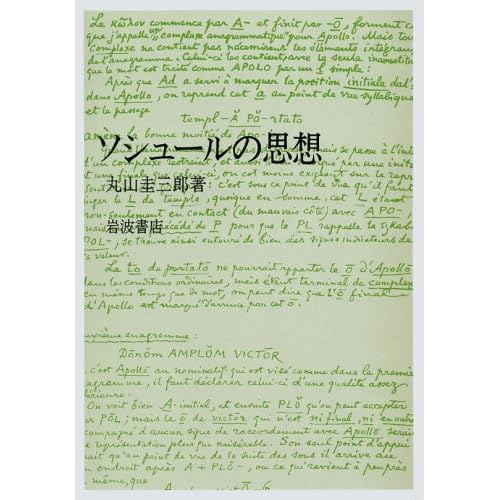
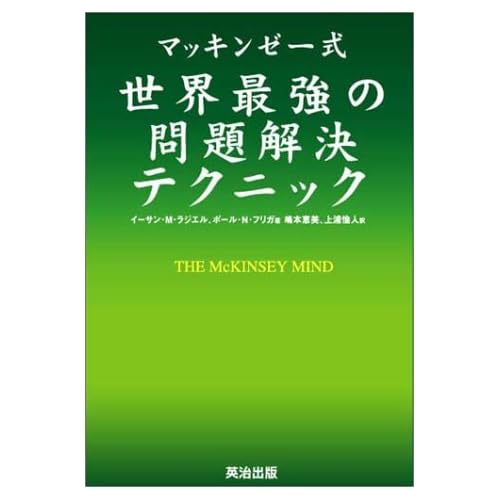





0 コメント:
コメントを投稿