僕は新聞・テレビ・週刊誌が大っ嫌いなので、大学生の頃からほとんど目にしないように努めている。
車で人を轢いてしまった女性アナウンサーが袋叩きにされ、
九州の高校の野球監督が体罰で袋叩きにされ、
柔道ナショナルチームの監督が選手に暴力を振るった角で袋叩きにされたのは知っている。
まったくもって、えんがちょ社会だ。ああ怖い。
時に、最近売り出し中の社会学者(評論家・編集者?)萩上チキさんがこんな本を書いた。
「朝まで生テレビ」で有名になったと聞き、しかもこのペンネームなので、ああ、また宮台真司的な何かかぁ、
と思ってスルーしていたのだが、見てみると意外と、というか至極全うな本を書いている。
言葉の軽いインチキ社会学者はわんさといるが、この人は、まともな印象だ。
きっと、社会学はウソをつき易い分野なのだと思う。なぜかと言うと、極端なこといったもん勝ちで、
仮説の検証・正当化という最も重要なフェーズに全く意識を払わない奴がごまんといるからなのだが、
その話は気が向いたら書こうと思う。
子どもへの暴力は容認されるか?
さて、今回のテーマは「子どもへの暴力は容認されるか」だ。
僕個人のレベルでは、「暴力なんて見るのもヤだから全部やめて」で十分だ。
よって、子どもへの暴力など、容認の余地は一切ない。おしまい。
ではまことに申し訳ないので、とりあえずこちらを読んでみてほしい。
メンバーの飯田が書いた記事で、手前味噌だがきっと率直に共感してもらえると思う。
「痛み」はもういらない
さて、これで話が終わればいいのだが、そうもいかない。そうもいかないのには、3つ理由がある。
理由その1 だめだと分かっていても、やめられない人がいる
理由その2 だめじゃないと本気で思っている人がいる
理由その3 「だめに決まってる。1、2のような人は特殊だから仕方ない」と思って、それ以上考えない人がいる
子どもへの暴力そのものを減らすためには、全部落とせない。
そして、これらは全て「暴力の正当化」というコンテキストに位置するテーマだ。そこで、この文脈から本を1冊を紹介しよう。
タイトル、しょぼいネ。・・・・・Σ( ̄⊥ ̄lll)・・・・・
というか出版社さん、このタイトルじゃ、ふつう誰も手に取らないでしょう。
しかも、なんと!!・・・これ、哲学書であるネ。ド━━━(゚ロ゚;)━━ン!!
( ̄▽ ̄)。o0○
・・・あ、やめよ、と思ったあなた!あと10秒読んでください。お願いプリーズ。
こんな本を出してきたのは、およそ”議論を正当化する”ということがどういうことかについて、注意を払ってもらいたいからだ。
なので、ちょっとだけ付き合ってほしい。
私が正しい!というための方法
当たり前だが、みんな自分の主張は正しいと思っている。それを人に分からせてやるために自説の正当化をするのだが、
議論の正当化には、いくつかの強力な方法がある。
①事実に訴える
例)被虐待児の就職率は、一般平均に比べて●●%低い
②感情に訴える
例)虐待された子どもを見たことがあるか! あんな残酷な姿は、もう二度と目にしたくない!この写真を見ろ!!
③ストーリーに訴える
例)他者への「責任=応答可能性」とは、他者への関係の中で自己を解体し、自己を根本的に再創造することを意味する。
主体の自らに対する不透明性の中には、主体と他者、主体と規範との強い関係が存在している。
それゆえに、古い規範=倫理の中に存在する倫理的暴力に対して、主体は批判的距離を保ち続けなければならない。
【注】3段落ちではありません!
世の中は不思議なもので、①に反応する人も②に反応する人も③に反応する人もいる。
そして、さらに不思議なことに、意図的に無視する人もいる。
正しさというのは、ぱっと見ほど一枚岩ではないのだ。だから、使い分けよう。
自分自身を説得するために、自分でない誰かを説得するために、その人に一番効く方法を探そう。
そして、それは自分には全く分からない動機から生まれている可能性がある。だから、分からないものにも耳を傾けよう。
僕が今日言いたいのは要するにそういうことだ。
この本の読み方もいろいろだ。
本の紹介をしておく。この本はゴリゴリのテツガク書。読みにくい。時間かかる。
でもテーマは、ぶっちゃけて言えば、
「教育的指導おぉぉ!!」と叫びながらぶん殴るのはアリかナシか、という話。
最初から読み始めれば、アドルノがあーしたのフーコーがどーしたの、レヴィナスがこーしたの、と書いてある。
で、人は社会的なルールを通じて他の人と繋がっていて、それはルールの押し付け暴力という形で相手を苦しめるけど、暴力はだめよ、と(たぶん)書いてある。
ほら、この構図、どこかで見たことありませんか?
そう、
本としては論旨は一本、叙述も清涼なので、まるでボルヴィック500mlを一気飲みしたような気分になれること請け合いだ。
こういう種類の本で、暴力論と聞いてまっさきに浮かぶのはデュルケムとかベンヤミンとかいったドイツ人の
名前だが、彼らが前景化しているのは国家による暴力だから一見違う話に見える。しかし、話は違わないのだ。
こういう人たちの説に共通しているのは、国家と国民というフレームだが、これがそのまま大人と子どもという構図に嵌る
からだ。もちろん当てはまらない部分もあるのだが、それを探すのも面白い。こういう風に読めば、自分とぜんぜん関係ない
と思われる岩波文庫の青いラベルとか講談社の紺色のラベルあたりの本も輝いて見えるかもしれない。
以上は、蛇足デシタ。
暴力に対してどうするか
正当化を振りかざすかぎり、論の掛け合いなんて何の意味もないと僕は思う。暴力には身体的なものと精神的なものが
あり・・・とか、暴力が必要な状況は確かにある、それは・・・とやっても、そもそもお互い相手の話なんか聞いていないし、
一方が一方を論破した(と誰かが主張した)としても、問題が消えない。なぜなら、
暴力とは、受けた側が受けたと感じた時点で発生するからだ。
はっきり言って、定義なんて関係ない。誰かが「私は暴力を受けた」と言えば、そこにはもう暴力が存在する。
それは、日常的な言葉の使用の、延長ではなく、内部にあるのだ。
暴力は常にその被害者から、問題意識がわきあがるがゆえに、問題であることを決してやめないテーマなのである。
だから、たぶん解決はない。じゃあどうするか?
論破ではなく、実害を減らそうと腐心すること、だと僕は思う。
実害とは、イヤだと感じた人が感じている当のことだ。正しいか正しくないか、ではなく、どうやって逃げるか、避けるか、
他の人に知らせるか、加害者にやめろと言うか、が大事。そしてそのために、協力を得ることが必要だ。
だからこそ、〈正当化という方法〉にも意識を払いましょう。人が信じている倫理に真正面から対抗してそれをぶっ壊そうと
するのではなく、ちゃんと話し聞いて協力者になりましょう。そして、ひとつひとつ目に見える実害を小さくしていきましょう。
そういう視点が大事なのだ。
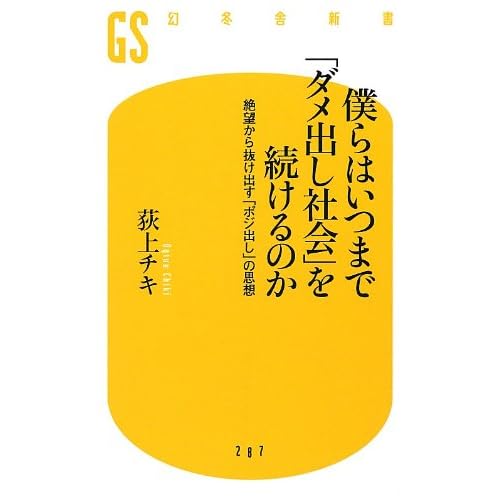






0 コメント:
コメントを投稿