(編集担当より)
みなさま、前回の板津につづき、「”問題”に出会う」と題しました書評リレーをお送りします。今回は、代表の慎の執筆です。
さて、このリレー・テーマについては前回の冒頭でご説明しましたが、じつはその依頼のさい、ひとつ付け加えたことがあります。それは各担当者が、身近で顔の見える友人・知人に手渡したい書籍を選んでほしい、ということでした。ですので、はじめて当ブログにいらして書評をご覧になった方々が、それでは、と気軽に書店や図書館などで、ご紹介の本や関連書籍を手にされるなら、それこそ望外の幸せです。そのため、もちろん気合いも入いります。しかし執筆は私ではありません。だから毎回、この前口上で一人盛り上がり・・・、そして空振りを繰り返すのです。(つづく)
私からの書評第一弾はこちらです。
本書は、虐待を受けた青少年と活動する多くの人々に多くの貴重な洞察を与えてくれると思います。それらは以下のように要約されます。
脳は、その発達の殆どを3歳までに終える。この時期に愛情を受けずに育つと、脳は多くの障害をもつようになり、その克服は年齢が高くなるほどに困難になる
本書は、死への直面、ネグレクト、暴力、レイプなどが子どもの心に及ぼす深刻な影響を様々な事例とともに記録しています。3歳になる頃には、子どもの脳の大きさは成人の85%にもなっているそうです。子どもの脳は急速に発達するため、様々なことを学んでいくことができますが、同様にひどい経験の影響も受けやすくなります。子どもの頃に受けた恐ろしい経験は、一生離れないトラウマに結びつきやすくなります。トラウマとまでいかなくても、何かが苦手な人は、子供のころに何らかの関連した経験をしている場合が多いそうです。本書には、非常に利己的な犯罪者になってしまった少年が登場します。彼も、決して生来の犯罪者だったわけではなく、子どもの頃の厳しいネグレクト(排泄の世話さえもちゃんとされていなかった)がその原因だったのではないかと著者は考えます。
子どもが立ち直るためには、ストレスに対して反応するための脳のシステムを鍛える必要があります。なんてことを言うと非常に難しそうですが、やるべきことは非常にシンプルで、子どもに愛情を注ぐこと、の一つに尽きます。本書に登場する傷ついた子どもたちのうち、立ち直れた子どもたちの共通点は、親や親代わりの人々が深い愛情をもってその子どもに接していることにあると著者は指摘します。特に、愛情とともに行われる抱擁などのスキンシップは、子どものこころを回復させるために大きな役割を果たしているそうです。
逆もまたしかりです。1940年代のある研究では、個別に注意を払って育てられなかった子どもの3分の1が二歳までに亡くなっていることを示しているそうです。また、幼少期に感情的な触れ合いや身体的なスキンシップを得られなかった人でない限り、極端な犯罪者になる場合は少ないと著者は指摘します。のみならず、問題のある子が、同様に問題のある人と過ごすことは、問題行動をエスカレートさせる傾向があると著者は指摘しています。
経済発展とコミュニティの強さは反比例することがあるようです。ですが、人間が本来どのような生物なのかを考えるのであれば、よりコミュニティの力を強くするための政策が必要なのではないかと著者は説きます。
脳は、気質(遺伝と子宮内環境に左右される)、幼児期の経験のみならず、偶然にも左右される様々な決断の積み重ねによって出来ています。ちょっとしたときに「善いこと」をするかしないか、の僅かな決断が、異なったフィードバックをもたらし、異なった結果を積み重ねることになります。
知能も重要な要素となります。情報を素早く処理する能力を知能と呼ぶのであれば、これは遺伝の影響を受けるものです。頭のよい子どもは対処能力が高いため、愛情を受けられなかった場合においても絶望的な状況から逃れられる可能性が高まります。もちろん、知能さえあれば正しい道を進める、というわけではないのですが。
本書の第七章では、子供に過去のトラウマを無理矢理に語らせることにより、症状がさらに悪化することがある事例が紹介されています。人それぞれ、トラウマに対するシステムを無意識のうちにつくりあげていて、そのあり方は人と場合によって異なり、同様に望ましい治療の仕方も人によって異なるのです。
無知な善意は時に害悪にも成りえます。改めて、自己肯定感を失ってしまった子どもたちのために活動をするのであれば、相応の知識が必要なのだと痛感させられました。
念のためですが、これは決して無知な人はこの領域に関わってはいけないということではありません。そうではなく、問題に対して真摯に向き合うのであれば、他の分野において私たちがしているように、学ぶことが大切だということを主張したいのです。そういったこともあり、私たちは初期においては特に頻繁に勉強会を開き、このブログにおいても書評を書いているのです。
みなさま、前回の板津につづき、「”問題”に出会う」と題しました書評リレーをお送りします。今回は、代表の慎の執筆です。
さて、このリレー・テーマについては前回の冒頭でご説明しましたが、じつはその依頼のさい、ひとつ付け加えたことがあります。それは各担当者が、身近で顔の見える友人・知人に手渡したい書籍を選んでほしい、ということでした。ですので、はじめて当ブログにいらして書評をご覧になった方々が、それでは、と気軽に書店や図書館などで、ご紹介の本や関連書籍を手にされるなら、それこそ望外の幸せです。そのため、もちろん気合いも入いります。しかし執筆は私ではありません。だから毎回、この前口上で一人盛り上がり・・・、そして空振りを繰り返すのです。(つづく)
私からの書評第一弾はこちらです。
(ブルース・D・ベリー、マイア・サラヴィッツ共著、紀伊國屋書店、2010)。
この本は、精神科医である著者が子供との邂逅を通じて学んだことを、自身の専門的見地から綴ったものです。1章から10章までは、著者が出会ってきた子どもたちのエピソードとそこからの学び、最終章である11章は、著者が児童虐待をめぐる社会の状況についての意見が述べられています。筆舌に尽くし難いひどい虐待の描写にも関わらず、全体的に温かみのある文になっているのは、著者の子どもたちへの眼差しが反映されているためかもしれません。本書は、虐待を受けた青少年と活動する多くの人々に多くの貴重な洞察を与えてくれると思います。それらは以下のように要約されます。
脳は、その発達の殆どを3歳までに終える。この時期に愛情を受けずに育つと、脳は多くの障害をもつようになり、その克服は年齢が高くなるほどに困難になる
本書は、死への直面、ネグレクト、暴力、レイプなどが子どもの心に及ぼす深刻な影響を様々な事例とともに記録しています。3歳になる頃には、子どもの脳の大きさは成人の85%にもなっているそうです。子どもの脳は急速に発達するため、様々なことを学んでいくことができますが、同様にひどい経験の影響も受けやすくなります。子どもの頃に受けた恐ろしい経験は、一生離れないトラウマに結びつきやすくなります。トラウマとまでいかなくても、何かが苦手な人は、子供のころに何らかの関連した経験をしている場合が多いそうです。本書には、非常に利己的な犯罪者になってしまった少年が登場します。彼も、決して生来の犯罪者だったわけではなく、子どもの頃の厳しいネグレクト(排泄の世話さえもちゃんとされていなかった)がその原因だったのではないかと著者は考えます。
(写真はブルース・D・ベリー。)
人間にはストレス耐性がありますが、それは日々の積み重ねによって徐々に強くなるものです。ストレス耐性がほとんどない子どもが非常に強いストレスに直面すると、自己防衛本能から様々な防衛行動をとることになります。抽象的思考などの人間の最も高度な知能部分を司る大脳皮質の活動は抑えられ、生存に必要な脳の中枢部分のみ機能するようになることなどがその一例です。こういった防衛行動は事件の一度で終わるものではなく、その後も、事件を彷彿とさせる出来事に直面する度に繰り返されます。失神してしまう(それによりストレスをシャットアウトする)、人との関わりを絶つ、自傷行為を行う(脳内麻薬を分泌させ、つらい思いから一時的に逃れる作用をもたす場合がある)、薬物にはしる、など、様々なパターンがあります。愛情が子どものこころを癒し自己肯定感を付与する
子どもが立ち直るためには、ストレスに対して反応するための脳のシステムを鍛える必要があります。なんてことを言うと非常に難しそうですが、やるべきことは非常にシンプルで、子どもに愛情を注ぐこと、の一つに尽きます。本書に登場する傷ついた子どもたちのうち、立ち直れた子どもたちの共通点は、親や親代わりの人々が深い愛情をもってその子どもに接していることにあると著者は指摘します。特に、愛情とともに行われる抱擁などのスキンシップは、子どものこころを回復させるために大きな役割を果たしているそうです。
逆もまたしかりです。1940年代のある研究では、個別に注意を払って育てられなかった子どもの3分の1が二歳までに亡くなっていることを示しているそうです。また、幼少期に感情的な触れ合いや身体的なスキンシップを得られなかった人でない限り、極端な犯罪者になる場合は少ないと著者は指摘します。のみならず、問題のある子が、同様に問題のある人と過ごすことは、問題行動をエスカレートさせる傾向があると著者は指摘しています。
(写真はマイア・サラヴィッツ)
著者は、虐待された子どもたちに最も必要なのは、幼少期のトラウマに起因する痛み、つらさ、喪失感を和らげてくれるコミュニティの存在だと説きます。トラウマから回復した子どもたちの周りには必ず、気にかけてくれる教師や、近所の人や、おばさんや、バスの運転手など、支えてくれる大人の存在があったというのです。コミュニティの存在は、愛情をもって接してくれる大人に出会う可能性を高めてくれます。難しいことは、児童虐待を受ける子供が、そのようなコミュニティの中に暮らす場合が少ないことです(それゆえに虐待が起こるという側面もある)。経済発展とコミュニティの強さは反比例することがあるようです。ですが、人間が本来どのような生物なのかを考えるのであれば、よりコミュニティの力を強くするための政策が必要なのではないかと著者は説きます。
子どもの人格は様々な要素で決まる
脳は、気質(遺伝と子宮内環境に左右される)、幼児期の経験のみならず、偶然にも左右される様々な決断の積み重ねによって出来ています。ちょっとしたときに「善いこと」をするかしないか、の僅かな決断が、異なったフィードバックをもたらし、異なった結果を積み重ねることになります。
知能も重要な要素となります。情報を素早く処理する能力を知能と呼ぶのであれば、これは遺伝の影響を受けるものです。頭のよい子どもは対処能力が高いため、愛情を受けられなかった場合においても絶望的な状況から逃れられる可能性が高まります。もちろん、知能さえあれば正しい道を進める、というわけではないのですが。
本書の続編である、
(ブルース・D・ベリー、マイア・サラヴィッツ共著、紀伊國屋書店、2012)。
誤った知識に基づいた善意は状況を悪化させる
本書の第七章では、子供に過去のトラウマを無理矢理に語らせることにより、症状がさらに悪化することがある事例が紹介されています。人それぞれ、トラウマに対するシステムを無意識のうちにつくりあげていて、そのあり方は人と場合によって異なり、同様に望ましい治療の仕方も人によって異なるのです。
無知な善意は時に害悪にも成りえます。改めて、自己肯定感を失ってしまった子どもたちのために活動をするのであれば、相応の知識が必要なのだと痛感させられました。
念のためですが、これは決して無知な人はこの領域に関わってはいけないということではありません。そうではなく、問題に対して真摯に向き合うのであれば、他の分野において私たちがしているように、学ぶことが大切だということを主張したいのです。そういったこともあり、私たちは初期においては特に頻繁に勉強会を開き、このブログにおいても書評を書いているのです。
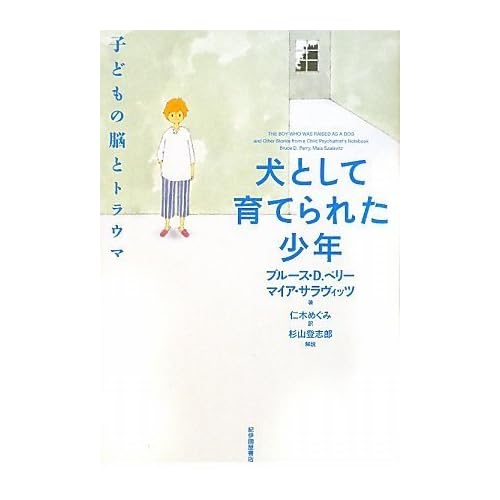


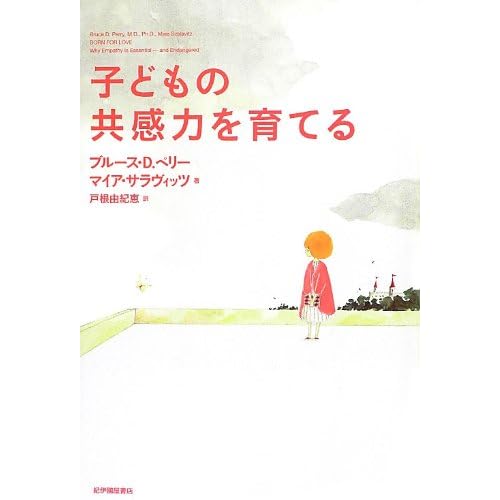




0 コメント:
コメントを投稿